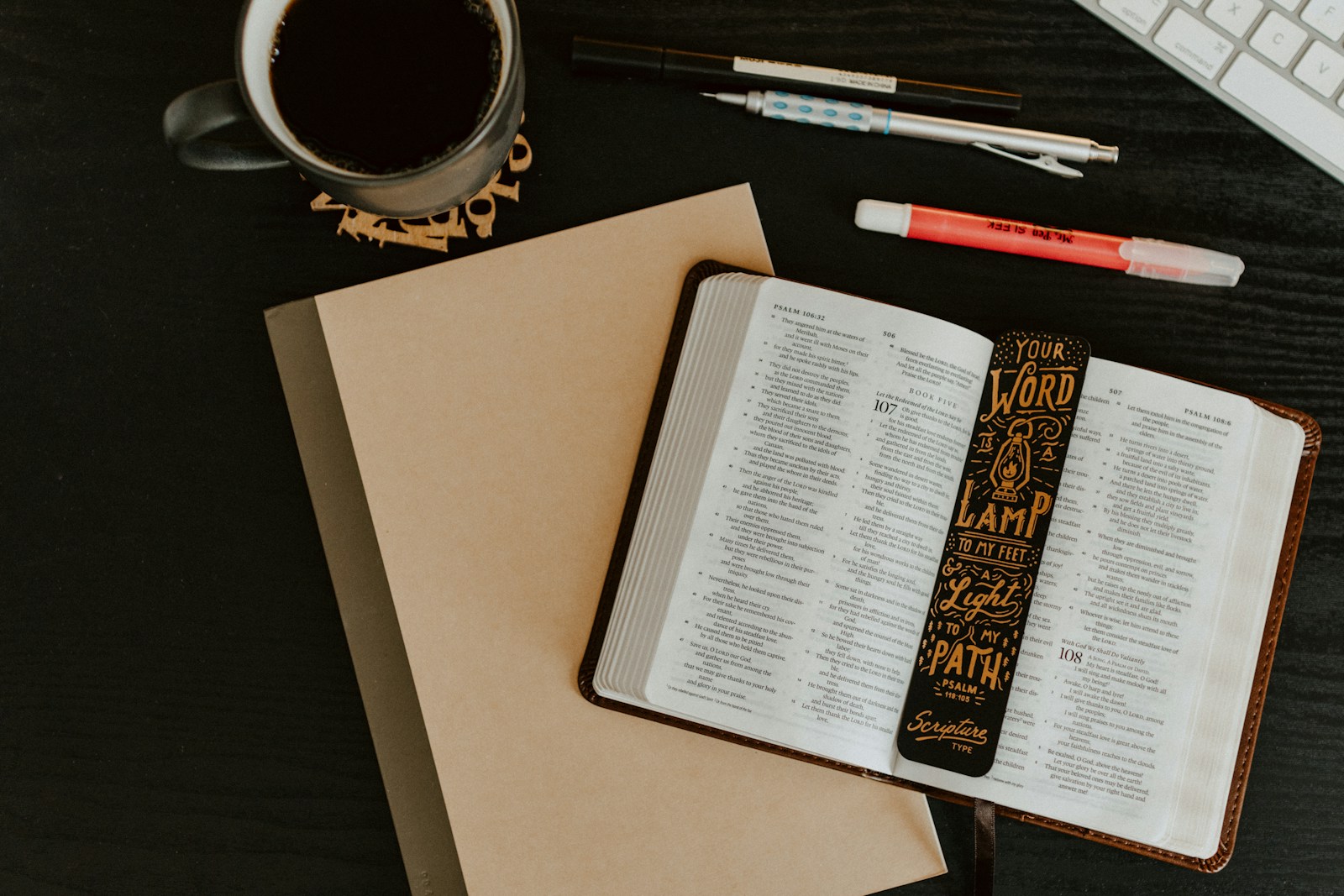後で読もうとして、X(Twitter)や、そしてスマホのブラウザや、各種サービスの「後で読む」にみなさん記事や情報が溜まっていませんか?
私もすごく溜まっています。
得た情報をX(Twitter)で発信している人たちもいますが、私は一旦このブログで発散していこうかなと思います。
なお、このブログを始める前から日々情報をストックし続けているため情報の新旧は順不同です。
また、あまりにも量が多いため、合間を見て小出し小出しで解放していきたいと思います。
目指せ、ストック全解放。
溜めた情報を解放
画像生成に関するプロンプト集がまとまっていますね。一定の法則が見出せそうです。一定の法則をAIに聞いて、適当な文章をその法則に変換するようにすると結構自由にいろんな画像が作れそうですね。

自分でGPTsを作ってみるのも面白いかもという記事。冒頭にあったクレイイラストのプロンプト試しましたが楽しいですよ。最初に目的に近いイラストを入れて、そこからプロンプトを打つことで自分の意図したものに近づけることができるいい例だと思いました。
これは本当にすごいですね・・・このプロンプトをどんどん改造すればもっと高クオリティなバナーが作れて、最低限はこれで十分になってしまいますね。

HTMXというものが世界で流行っている、という記事を見ました。その割にはあまり検索しても出てきませんね、日本ではまだこれからかも知れません。
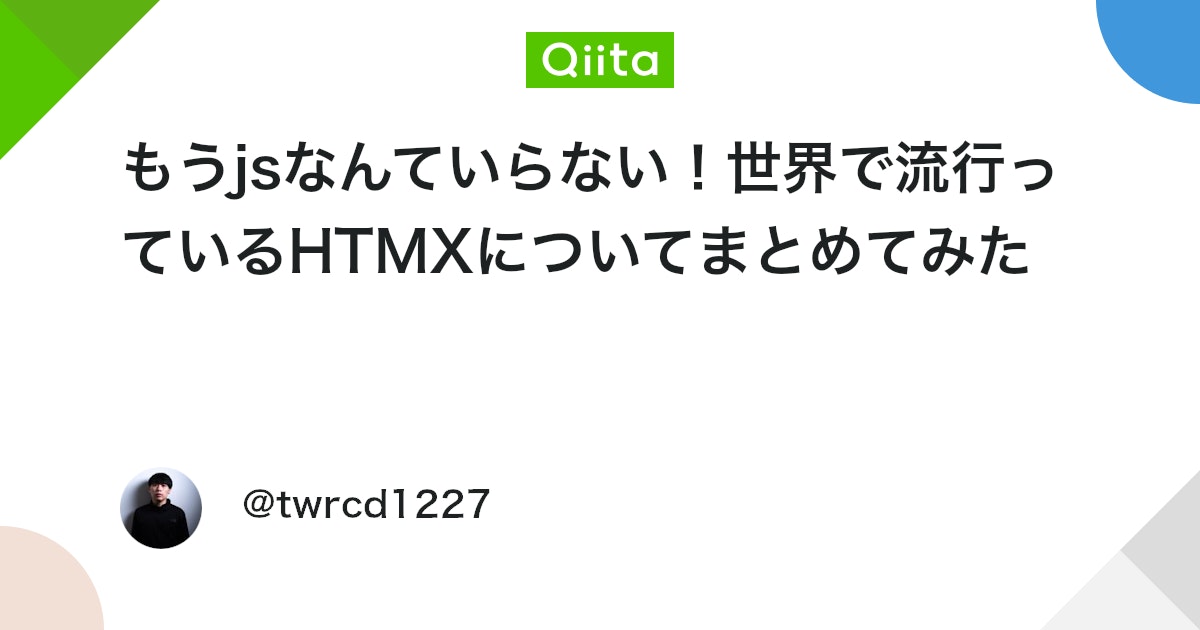
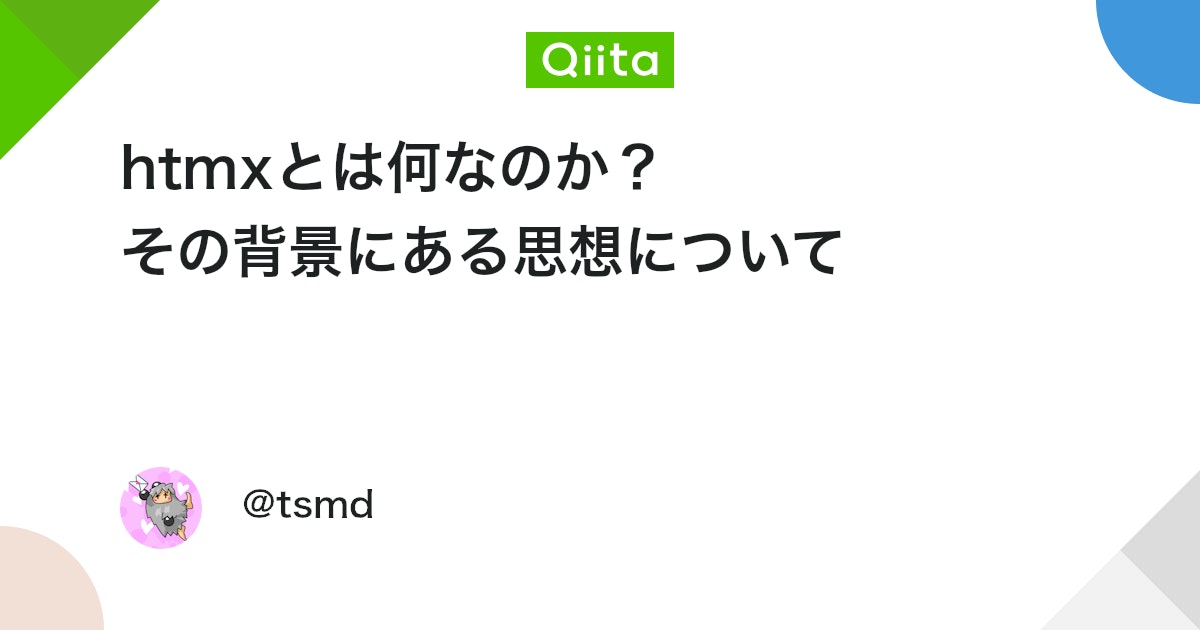
使用されているjavascriptのトレンドがサクッとわかるこちらのサイトが便利ですね。HTMXが24年ではReactより高いのに、まだ試してみた系の記事が多い印象です。
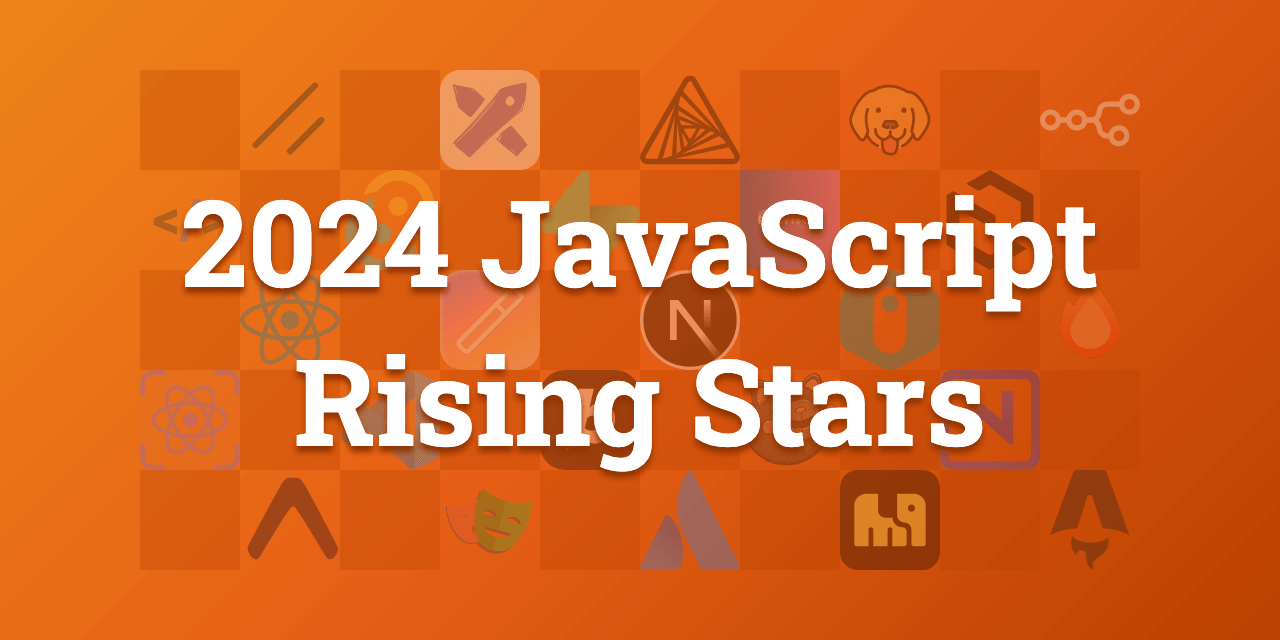
これ系のフォントの記事は埋もれてしまうのでブックマークしておくと良いですよね。ただフォントを紹介するだけではなくなぜいいかが書かれているので、選んだ際に説明責任を果たせます。

ポモドーロテクニックではなくフロータイムテクニックが良いですよという記事。個人的にはずっとその作業だけすることができないのでポモドーロがベースであり、勢いが良い時のみフロータイムを取り入れるのがよいかもという所感です。やりたくないけどやらなきゃいけない作業をフロータイムでやると途中で辞めてしまうので、そんなときは決められた時間をやりきったら休憩という報酬があるポモドーロテクニックのほうが良いと思っています。
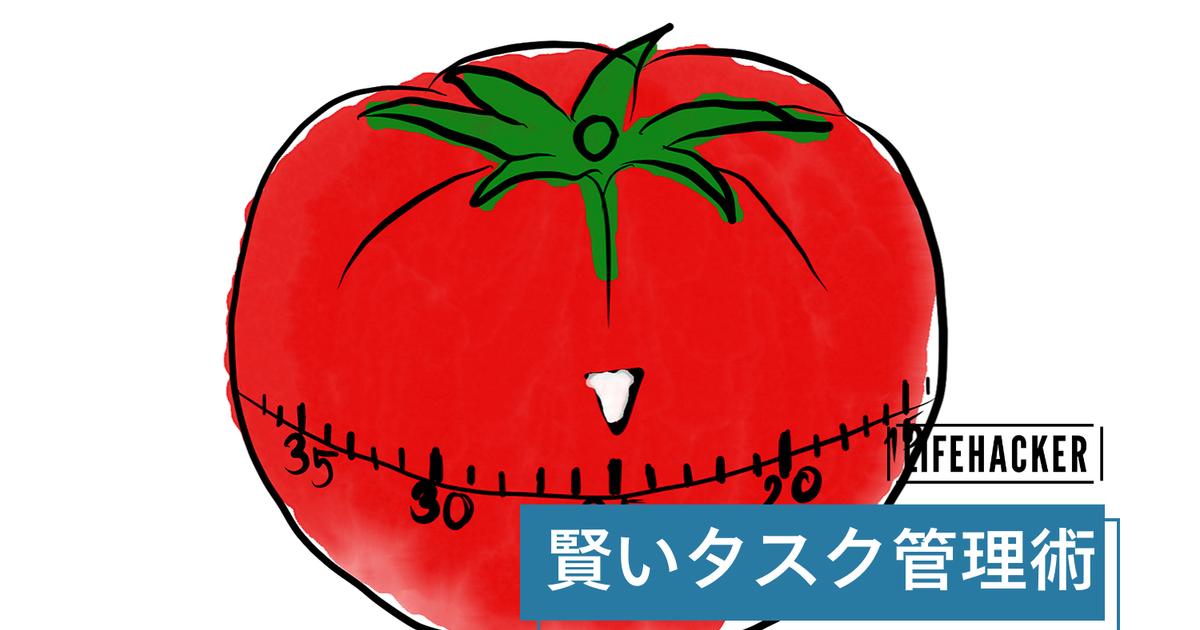
意外と無意識に使っていた「」や()など、しっかりと振り返ることでクリエイティブを作成する際の約物の取り扱いに改めて注意してデザインができるのではないでしょうか。ライティングする際にも有効かと思います。
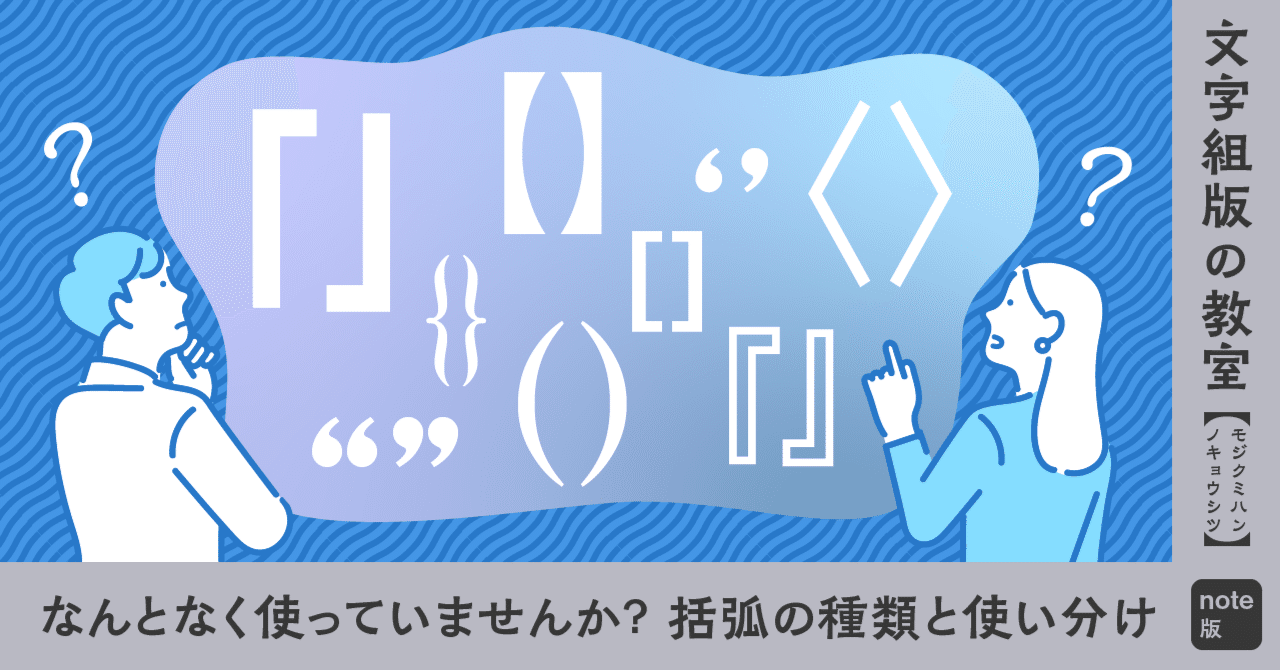
バーチャルプロダクトプレイスメントという、動画内にAIで商品を埋め込む手法が面白いです。実際の実例もあるので、動画コンテンツを作る際に参考になりそうです。

プロンプトエンジニアリングが苦手な時にPrompt Perfectを使うのも良いかもという話。出力結果がうまくいかないとき、試すと良さそうだなと思います。